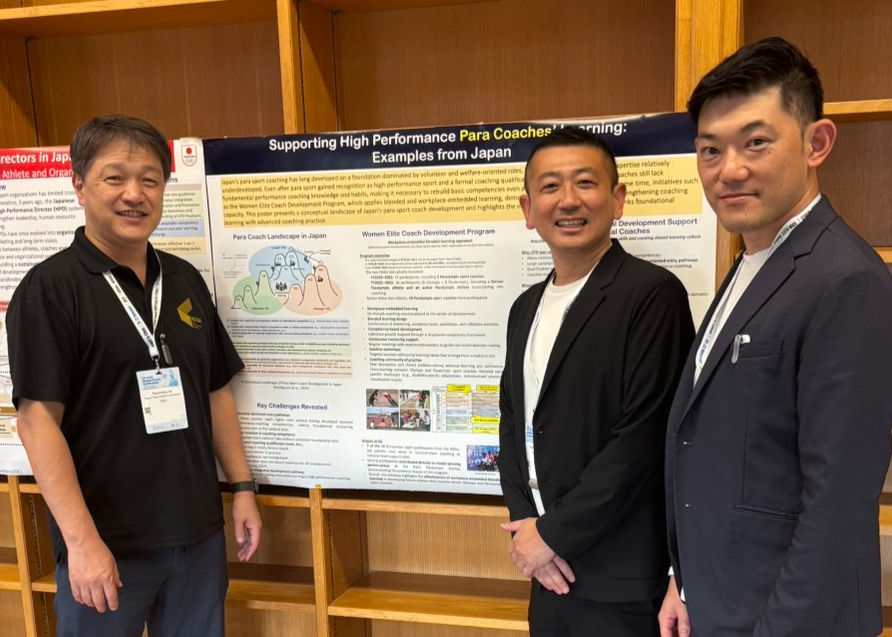Application Scienceとしてのコーチング学
- 伊藤雅充

- 2025年11月24日
- 読了時間: 5分

コーチング学とは何をする学問なのか?
日本体育大学で大学院のコーチング学系を設置した際、国内外の多くの専門家と議論を重ねました。そこで得た感覚は、今もなお私の中に強く残っています。私はコーチング学を「コーチング実践に直接関わる学問」として捉えています。かつて私が取り組んでいたバイオメカニクスや運動生理学、トレーニング科学は、広義のコーチング学に含まれる重要な分野であるものの、それ自体がコーチング学ではありません。コーチングに“役立つ”学問であっても、コーチング学“そのもの”とは異なる。私はそう考えています。
今回は、その考え方が形成される上で重要な影響を与えた経験について紹介します。
イギリス訪問で得た気づき
日本体育大学は平成23〜25年度に「文部科学省大学スポーツ研究活動資源活用事業」を受託し、体育教師およびコーチの専門能力向上に関する研究を行う機会を得ました。特にコーチング能力に関する部分は「コーチ実践指導力の向上プログラム開発」というテーマで調査・研究を進めました。
その一環として、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなど、各国のコーチ育成システムの調査を行いました。イギリスではリーズ・メトロポリタン大学(国際コーチングエクセレンス評議会[ICCE]事務局)とラフバラ大学を訪れ、コーチング学の捉え方について貴重な意見交換を行いました。
John Lyle氏との議論

訪問の中でも、最も大きな示唆を得たのが John Lyle 氏とのディスカッションでした。コーチ教育とコーチング研究の本質をめぐる議論が中心となり、彼は明確にこう述べました。
「コーチングは Applied Science ではなく、Application Science である」
バイオメカニクス、生理学、心理学などのスポーツ科学は、アスリートのパフォーマンスを理解する上で有益な情報を提供します。しかし、それらは「コーチングそのもの」を扱っているわけではありません。コーチングは介入(Intervention)であり実践です。したがって重要なのは「アスリートにどのように関わるか」であり、そのHOWを扱う学問であるべきだ、というのがLyle氏の主張でした。
Lyle氏によれば、スポーツ科学は数学、物理学、医学といった Pure Science (純粋な科学、基礎科学)を基盤とした Applied Science (応用科学)です。しかしコーチングはその延長線上にあるものではなく、そこから一歩前に踏み出した Application Science(適用の科学) でなければならない。
Applied Science:What to do を扱う
Application Science:How to do を扱う(=コーチング)
そして、この「How to do」は、コーチが活動する現場そのもので扱われる必要があり、実験室に持ち込む研究では、様々な文脈的要素が欠落するため、本質的なコーチの“判断”や“意志決定”の研究にはならないという指摘も印象的でした。

コーチング“学”が抱える性質
こうした性質をもつコーチング学では、ある場面で得られた結果を別の場面にそのまま一般化することは困難です。典型的な自然科学が重視する「普遍性」や「再現性」をそのまま求めることが難しいのです。
このディスカッションは、「コーチング学とは何か?」という私自身の長年の問いに明確な方向性を与えるものでした。以前、私自身が行っていたアスリート対象の研究を「コーチング学」と呼ぶことに抵抗を感じていた理由にも、ひとつの答えが与えられた瞬間でした。
現在私は、パフォーマンス分析、バイオメカニクス、生理学、心理学などはコーチングに役立つ学問であるが、それ自体はコーチング学ではないと捉えています。ゼミや大学院生が私の元で研究をしたいと申し出てきた際には、この点を強調しています。例えば、もし学生がパフォーマンス分析をやりたいと申し出てきた場合には、そのパフォーマンス分析をコーチがどう活用するかであれば私のところでよいけれども、パフォーマンス分析そのものをやりたいのであれば、トレーニング科学の教員に指導を仰ぐ方がよいと。
私の立場は、ICCEが2年に1度開催する世界コーチ会議の研究採択基準とも合致するものと言えます。私もICCEの科学委員を務めていたことがありますが、会議での発表が認められるかどうかの基準が明確に示されています。コーチを対象としていない研究は、スコープ外としてリジェクトされることがほとんどです。その研究を扱う学会は他にあるというスタンスです。
一方で、日本の学会やアジアコーチング科学協会の会議では、依然としてアスリート対象の研究発表が多いのも事実です。しかし、近年は「コーチを対象とした研究」が少しずつ増えてきていることも感じており、仲間が増えてきたなと実感を得ています。
このように、Lyle氏との議論は、私自身の考えるコーチング学に関して、進むべき方向を考えるのに大きな手がかりとなりました。ただ、私はこの考えが正しいと言っているのではなく、あくまでも私が研究や教育活動をする際のベースとなる考えであるということを言っています。私たちの研究室でコーチング学を学ぼうと考えている方々に、そのスタンスを知っておいていただければと思います。
(参考文献)
日本体育大学コーチ実践指導力の向上プログラム開発プロジェクトチーム「平成23年度「文部科学省大学スポーツ研究活動資源活用事業 コーチ実践指導力の向上プログラム開発報告書」2012 (H24) 年3月